テーマ:プラスチックごみを考える
話題提供者:兼松 方彦さん
今回は、「環境の杜こうち通常総会」第2部として、兼松方彦さんに登壇いただき、プラスチックの生産から回収の問題まで、分かりやすい資料をもとに講演していただきました。
プラスチックの原料は、原油を精製する過程で生産される「ナフサ」です。そのナフサを加工・分解し、得られたものを結合すると、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)、ペットボトルに多く使われるポリエチレンテレフタレート(PET)などの素材になります。特にPETは透明で強度があり、薬品にも強いという性質を持っています。
日本では年間およそ800万トンのプラスチックごみが出ています。そのうち、再び原料に戻す「マテリアルリサイクル」は約2割、化学原料に再生する「ケミカルリサイクル」は3〜4%にとどまり、半分以上が「サーマルリサイクル(燃やして熱エネルギーに変換)」に頼っているのが現状です。つまり、焼却に大きく依存しているのです。
物部川流域で実施した調査結果によると、外海沿いでは、特にペットボトルや容器包装のごみが多く、ラベルが剥がれていて発生源を特定できないものも多数見られました。PET素材自体は水に沈むため、キャップの状態で浮沈が変わるなど、回収の難しさとともに、生態系に及ぼす影響や人体への健康被害が懸念されています。
近年では、海洋ごみだけでなく農業由来のごみも課題となっており、水稲の肥料に使われる被覆材(中空ポリエステル)が微細となって流出し、シラス漁の妨げになるケースもあるそうです。行政の認識が十分でないことも課題として挙げられました。
最後に「これからは“リデュース・リユース・リサイクル”の3Rに加えて、“Renewable(再生可能資源への転換)”の考え方が大切です」と述べられました。
今回の講演では、私たちが暮らしの中でできること、使い方、処理(リサイクル)、回収・清掃活動への参加などについて考えさせられました。行政だけでなく、地域の人々や企業が力を合わせて取り組むことが、これからの鍵になりそうです。
(2025年6月7日)
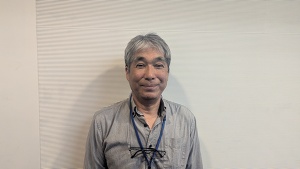
プロフィール:兼松 方彦(かねまつ まさひこ)
物部川21世紀の森と水の会 事務局長、高知県地球温暖化防止活動推進センター センター長、NPO法人 環境の杜こうち元理事長。物部川流域等のごみ清掃・調査活動のほか、高知県内外の自治体職員研修において地域計画策定の講師やワークショップファシリテーターをつとめるなど多方面で活躍。
プラスチックの原料は、原油を精製する過程で生産される「ナフサ」です。そのナフサを加工・分解し、得られたものを結合すると、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)、ペットボトルに多く使われるポリエチレンテレフタレート(PET)などの素材になります。特にPETは透明で強度があり、薬品にも強いという性質を持っています。
日本では年間およそ800万トンのプラスチックごみが出ています。そのうち、再び原料に戻す「マテリアルリサイクル」は約2割、化学原料に再生する「ケミカルリサイクル」は3〜4%にとどまり、半分以上が「サーマルリサイクル(燃やして熱エネルギーに変換)」に頼っているのが現状です。つまり、焼却に大きく依存しているのです。
物部川流域で実施した調査結果によると、外海沿いでは、特にペットボトルや容器包装のごみが多く、ラベルが剥がれていて発生源を特定できないものも多数見られました。PET素材自体は水に沈むため、キャップの状態で浮沈が変わるなど、回収の難しさとともに、生態系に及ぼす影響や人体への健康被害が懸念されています。
近年では、海洋ごみだけでなく農業由来のごみも課題となっており、水稲の肥料に使われる被覆材(中空ポリエステル)が微細となって流出し、シラス漁の妨げになるケースもあるそうです。行政の認識が十分でないことも課題として挙げられました。
最後に「これからは“リデュース・リユース・リサイクル”の3Rに加えて、“Renewable(再生可能資源への転換)”の考え方が大切です」と述べられました。
今回の講演では、私たちが暮らしの中でできること、使い方、処理(リサイクル)、回収・清掃活動への参加などについて考えさせられました。行政だけでなく、地域の人々や企業が力を合わせて取り組むことが、これからの鍵になりそうです。
(2025年6月7日)
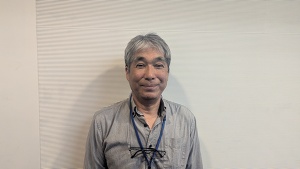
プロフィール:兼松 方彦(かねまつ まさひこ)
物部川21世紀の森と水の会 事務局長、高知県地球温暖化防止活動推進センター センター長、NPO法人 環境の杜こうち元理事長。物部川流域等のごみ清掃・調査活動のほか、高知県内外の自治体職員研修において地域計画策定の講師やワークショップファシリテーターをつとめるなど多方面で活躍。

